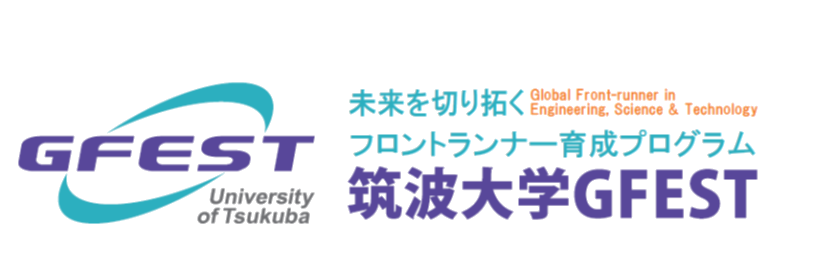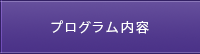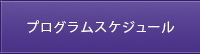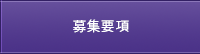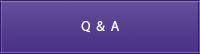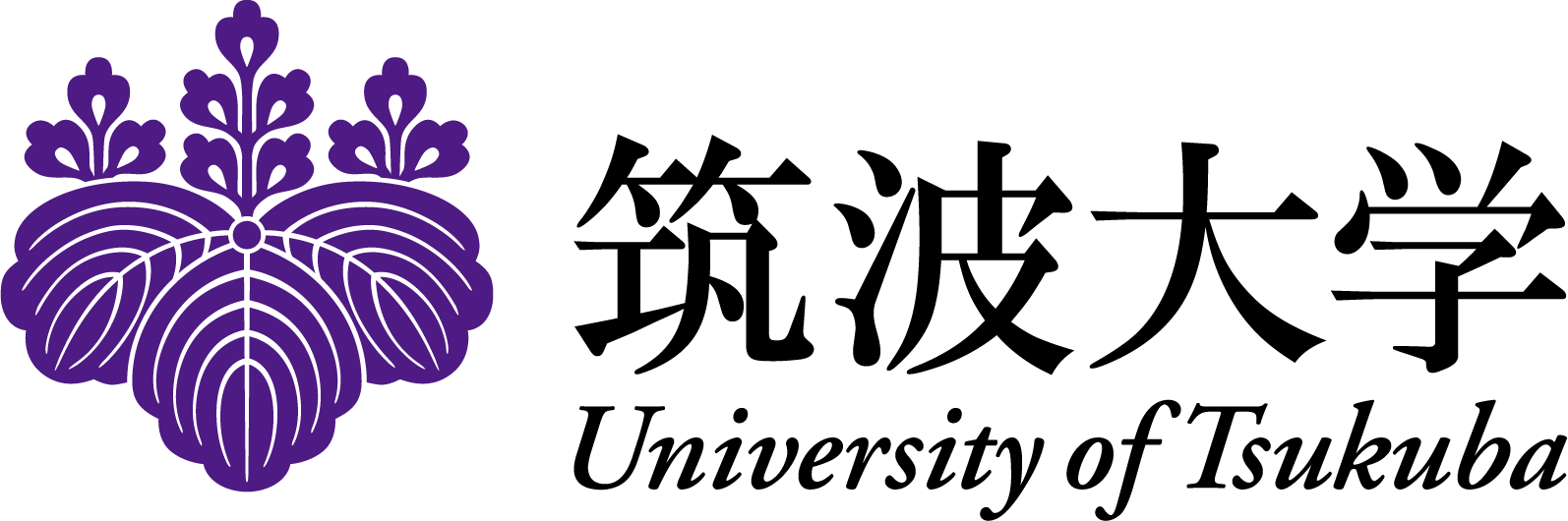2025年8月5, 6, 7日の2泊3日の日程で、GFEST「夏の実習」を開催しました。
【1日目内容】
・開会の挨拶 プログラムリーダー:相山 康道 教授
・研究倫理講義 講師:岡林 浩嗣 准教授(生存ダイナミクス研究センター)
・受講生交流
・研究室での研究体験とレポート作成






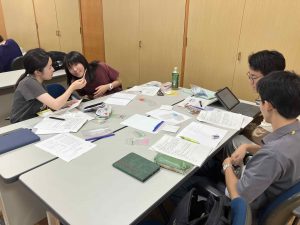

下記の研究室にお世話になりました。ありがとうございました!
マニピュレーション・システム研究室 相山 康道 教授
生物圏変遷科学分野 上松 佐知子 准教授
生体計測システム研究室 前田 祐佳 准教授
無機合成化学研究室 志賀 拓也 准教授
微生物サステイナビリティ研究センター 豊福 雅典 准教授
数理物質系物資工学域 松石 清人 教授
動物系統進化・進化発生学研究室 守野 孔明 助教
食品機能化学研究室 吉田 滋樹 准教授
<受講生の感想_研究倫理講義>
★不正や改ざん、盗用などの研究倫理違反の行為から、研究対象の保護や、公正な研究結果を保証するために必要な回数など、一言に研究倫理といっても範囲は広く、私自身の研究も決して他人事ではないということを感じた。
★研究において自分が不正しようと思っていなくても、ちょっとしたミスが不正につながってしまうことがあるということで、注意しなければならないと思った。不正を防ぐためには、誠実に結果を記録・保管し、オープンな議論をするようにし、時間的に余裕を持って行動するのが大切ということだったので、将来、間違いを犯さないよう今から意識づけていきたいと思った。
★データの取り扱い方についてはほぼ全ての研究に関連するテーマであり、私の研究にとっても例外ではないと気づきました。データの扱いによって、研究の信頼性や妥当性、再現性などの要素が左右されると気付かされため、これからの課題として改めて考え直す必要があると感じました。岡林先生が仰られていたように、常日頃から先生や友達とオープンな議論を交わすことを意識し、意図しない不正を未然に防ぐことを徹底したいです。
<受講生の感想_研究体験>
★全体を通して強く感じたのは、「実験そのものの面白さ」である。学校の授業で行う基礎的な実験とは異なり、研究室の実習では専門性が高く、また未知の現象に直接触れることができる。そのため、一つ一つの結果が驚きと発見につながり、純粋に化学の世界の奥深さを体験することができた。
★特に生物学に関しては、普段触れている多細胞生物ではなく、単細胞生物について学ぶことができた。小さなバクテリアの世界であっても、個体によって持っている役割が異なっており、その役割分担によってバイオフィルムができているというのが興味深かった。
★なによりも印象に残ったのが、古生物学を学ぶことで、その生き物の当時の習性や暮らし方がある程度予測できてしまうことです。たったの骨数本で、その生き物の見た目や運動方法、またそこからどんな生活をしていたのかが推定できてしまうのは本当に感動しました。